尾鷲ダイビングエッセイ〜尾鷲の色〜

沖縄に居を構える水中写真家・上出俊作さんによる、海とダイビングにまつわるエッセイをお届けします。
三重県のダイビングスポット、尾鷲へ。
水中写真に思いを巡らせながら、上出さんにとっての“幸せ”を思う。
そして、少々の杞憂と共に潜った尾鷲の海で目にした輝きとは?
尾鷲へ
ノイズに負けそうな音楽が、外から聞こえてくる。
どこにスピーカーがあるのかわからないけれど、割と近くにあるようだ。
朝7時の町内放送。
何回聞いても、何の曲だかわからない。
だいぶ田舎に来たんだな、と思う。
僕が生まれ育った街には、朝の町内放送はなかった。
現在暮らしている沖縄本島の名護にも、やはりない。
前に町内放送で目覚めたのはいつだっただろうか、とぼんやり考えていると、夏の伊平屋島の光景が頭に浮かんできた。
伊平屋島といえば、開発が進む沖縄の離島の中では数少ない、手つかずの自然と暮らしが残る島。
沖縄本島からフェリーで2時間。
そこには、時間が一度止まってまた動き出したような、ノスタルジックな空気が漂っている。
伊平屋島でも、町内放送で目覚めるのが日課になっていた。
どんな曲が流れていたのかは、忘れてしまったのだけれど。
屋外スピーカーからの音が鳴りやむと、僕はベッドからムズムズと這い出した。
冷蔵庫の中から缶コーヒーを取って、外に出る。
快晴だ。暑くもないし、寒くもない。
梅雨前線は、まだまだ南の方にいるらしい。
海に向かって歩いていくと、甘い声を響かせながら猫が近寄ってきた。
餌が欲しいのだろうか。あるいは、単なる朝の挨拶のようなものだろうか。
僕には猫の気持ちがわからないし、あげられるようなものは何も持ち合わせていないから、気にせず歩いていく。
30歩ほどで海に着いた。
船外機をつけた漁船が数隻係留されている、地元漁師のための小さな港だ。
港には誰もいない。
辺りを見渡してみると、50メートルくらい先に、歩いているおばあさんが見えた。
この町に来てから、おばあさんばかり見かける気がする。
特にすることもないので、僕は半分残ったコーヒーを手に部屋に戻った。
三重県尾鷲市行野浦。
映画のワンシーンに出てきそうな、絵に描いたような小さな港町。
3日前、僕はこの集落にやってきた。
今のところ同年代の住人には一度も会っていない。
とはいえ僕は朝と夕しかこの辺りを歩いていないから、もしかすると日中は若者で溢れかえっているのかもしれない。
などと思いを巡らせてみたのだけれど、きっとそんなことはないのだろう。
紀伊半島の東側。コンビニもスーパーもない、静かな港町。
僕にとっては、それだけでなんだか、お忍び旅行に来たような気分になる。
夜になれば、町は完全な沈黙に包まれる。そこには静謐さすら漂っている。
今の時代、この静けさを感じられるだけでも贅沢なことだ。
とはいえ実際には、お忍び旅行を受け入れられるような宿はここにはなく、過疎という現実的な問題が横たわっている。
「地元を盛り上げたい」
2022年の秋、尾鷲のダイビングショップTRUE COLORの伊藤英昭さんからそんな話があった。
伊藤さんは幼少期を尾鷲で過ごし、ダイビングガイドとして尾鷲の海を30年近くガイドしてきた、まさに尾鷲の人。
三重の海は、ダイバーの間では以前よりも認知されるようになってきていると思う。
しかしそれでも、ダイビングメッカの隣県和歌山には遠く及ばない。
人が減りつづけ、空き家ばかりが増え続ける町は、その存続自体が危ぶまれているのかもしれない。
尾鷲を盛り上げるために上出さんの力を貸してほしい。
それは伊藤さんからの、真剣な、切実なお願いだった。
短い人生の中で、誰かが自分を本気で必要としてくれることが、どれだけあるのだろう。
幸せなことだな、と思った。何者でもなかった僕が、気づけばこうして求められている。
写真家として、作品をつくっていく上では、期待に応えることが仕事ではない。
でも、人と人との関係の中で、写真を通して誰かの期待に応えられるのなら、それは素敵なことだなと思った。

僕にとっての幸せ
2023年5月。僕は尾鷲市行野浦のカラーハウスにいる。
カラーハウスというのは、伊藤さんが空き家をリノベーションして作った、TRUE COLORのクラブハウスのこと。
カタカナで書くとカレーライスみたいで野暮ったいけれど、実際には古民家のあたたかい雰囲気を残しながら綺麗にリノベーションしていて、とても居心地がいい。
尾鷲に来てから、僕はカラーハウスで寝泊まりしている。
そしてこの場所で、週末にはゲストを集めて、フォトセミナーが開催される。
セミナーを開催するにあたって、伊藤さんが事前アンケートを取ってくれていた。
「上出さんへの質問はありますか?」という設問に対して、参加者の一人からこんな質問があった。
「水中写真とは?」
水中写真とは何だろうか。
もちろん、一言で答えられるようなテーマではない。
僕たちが生きる世界の中で、水中写真とはどういう位置づけなのか。
芸術という分野の中で、あるいは写真という表現の中で、水中写真の価値とは何なのか。
そういうことは、論じられるべきだろう。僕ももっと、深く考えなければいけない。
でもそれ以前に、自分にとっての水中写真とは何なのだろう?
少なくとも、僕にとって水中写真は、仕事ではない。
職業は何かと尋ねられれば水中写真家と答えるし、これといって他に仕事があるわけでもないから、それ自体は嘘でもなんでもないのだけれど。
仕事は水中写真だけど、水中写真は仕事ではない。
矛盾しているようで、していないはずだ。
因果のなんとかという話である。
僕は水中写真を撮っている時間が、好きで好きでたまらない。
それは10年以上変わらないし、むしろ、水中写真を撮り始めた頃よりも、今の方がその気持ちが強い。
自分にとって、唯一続いている、熱くなれる趣味と言っていいだろう。
そう、水中写真は仕事というより趣味なのだ。
今も趣味の延長で仕事をしている。
大好きだから熱中するし、手は抜かない。常に完璧を求めている。
僕はあまり生真面目な性格ではないから、やらされている仕事だったら、こんな風には取り組めない。
これまでの人生、本気になれないものばかりだったから、自分でもよくわかる。
小学生の時に始めたサッカーは、なんだかんだで大学のサークルまで続けた。
でも、一度も主体的に練習に取り組んだことはなかったし、誰にも言えなかったけれど、試合に出られなくても、チームが負けても、悔しいと思わなかった。
結局もう10年以上ボールは蹴っていないし、蹴りたいという気持ちもない。
新卒で入った製薬会社は、いい会社だった。
尊敬できる同僚や先生とも出会えて、今も交流が続いている。
でも、5年間の営業生活の中で一度も、誰かに勝ちたいとは思わなかった。
競合との勝負を放棄し、社内での勝負も放棄した営業マンに、仕事へのモチベーションはない。
会社員時代は、夜のBARホッピングと、休日のダイビングだけが生きがいだった。
他にも、なんとなく始めて、中途半端にやめたものがたくさんある。
自分で目標を決めて本気で取り組み、何かを成し遂げたという経験が、僕には一つもなかった。
受験も就活も、遊びもスポーツもどれもそれなりで、どこか自分に自信が持てない人生だった。
そんな自分が、気づけば水中写真家として胸を張って生きている。
自分を応援してくれる人も、求めてくれる人もいる。
目標に向かって挑戦し、何かを成し遂げるということも、少しずつできるようになってきた。
水中写真と出会えてよかった、と心から思う。
自分が今「生きている」と感じる。
水中写真に感謝!なんて言うと気持ち悪いけれど、でも、それが本心だ。
水中写真と、水中写真を通して出会った人たちから、僕はたくさんのものを与えてもらった。
これからは、水中写真を通して、世の中に価値を生み出し続けたい。
誰かを喜ばせて、期待にこたえて、自分が与える側になりたい。
その結果、水中写真が自分の人生そのものになっていたら、それは僕にとって何よりも幸せなことだ。

杞憂
「尾鷲の海の暗いイメージを変えたい」
去年から伊藤さんは何度も、僕にそう伝えてくれていた。
僕は沖縄で暮らしていて、普段から明るい海で潜っているので、「暗い海」と言われると、なんだか本州っぽくていいなと思ってしまう。
けれども、一般的には「暗い」というのはそれほど好まれるイメージではないのだろう。
だからと言って、「実際には暗くないですよ!」と叫んでみたところで始まらない。
というか、それは嘘だ。もちろん明るい時だってあるだろうが、串本に比べれば暗いし、当然沖縄よりも暗い。
でも、それはあくまでパッと見た時の印象だ。
視点を変えれば、見える景色は変わる。
そして、新しい視点を提供することこそが、写真家に課せられた最も重要な仕事だと思う。
見方によっては、暗い海も明るく華やかな世界に変わるだろう。
とはいえ僕は普段、海に入る前から「こう撮ろう」と決めることはない。
水中で生き物と対峙して、感じたことをどうやって表現するか、その場で考えたい。
生き物たちが持つ魅力を、それが少しも損なわれないように写真に乗せる。
そのために、自分の中にあるどの引き出しを開けるのか、現場で選択する。
それが僕にとっての水中撮影だ。
写真が明るいとか暗いとか、くっきりしているとかふんわりしているとかいうのは、あくまでどの引き出しを開けたかの結果。
それは生き物たちの魅力を引き出すための手段に過ぎない。
だから、最初からどう撮るかは決めない。
でも、たまには手段と目的が入れ替わったっていいだろう。
水中写真のおかげで、僕はここにいる。
今は水中写真を通して、期待にこたえたい。
「自分なりに尾鷲の海を明るく表現してみよう」
そう思いながら、尾鷲の海を潜った。
ボートからエントリーして、アンカーロープを辿りながら、巨大な根のトップまで降りる。
そこからさらに、水深15メートルの水底まで、北に向かって潜降していく。
僕は着底して、自分が降りてきた根をそっと見上げた。
その瞬間、気負う必要などなかったことに気づかされた。
人間の頼りない想像力や信念なんて、時に自然の前では意味をなさない。
目の前の壁には数えきれないほどの色たちが散りばめられ、それはまるでジャクソン・ポロックによって描かれた絵画のように、野性的な輝きを放っていた。





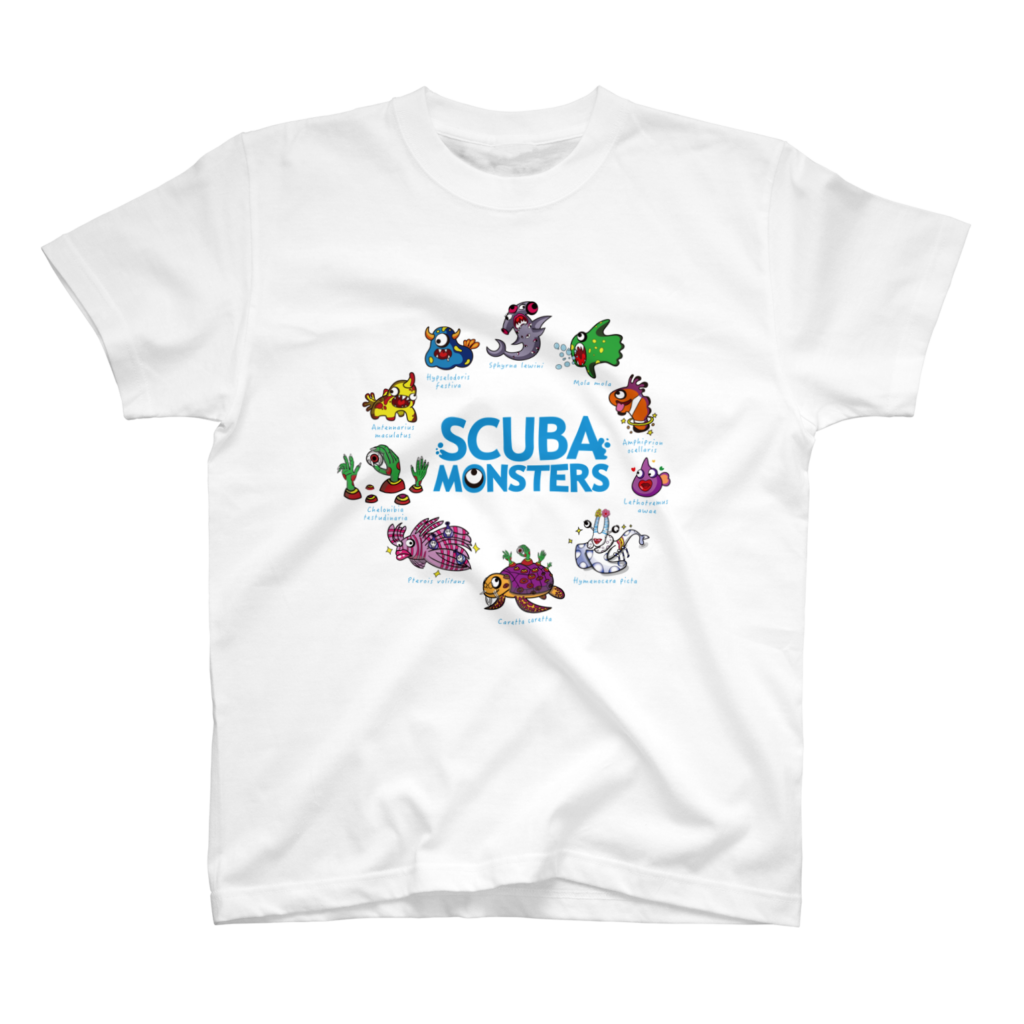


















この記事へのコメントはありません。