アラスカフォトエッセイ〜長い旅の始まり〜

沖縄に居を構える水中写真家・上出俊作さんによる、海とダイビングにまつわるエッセイ連載。
今回は、番外編をお送りします。
思い焦がれていたアラスカへの旅を実現させた上出さん。
そこで過ごした心情を丁寧に素直に綴ってくださいました。
読書の秋。
ぜひ、ゆっくり文章に身を委ねてみてくださいね。

アラスカの地
正面にブローが上がったかと思うと、3時の方向にもブローが見えた。
アメリカ本土からクルーズ船で来たと思われる紳士が、ボートの後ろにもいるぞと指をさす。
無視するのも感じが悪いので一応振り向くと、すでにブローは消えていて、1頭のザトウクジラが尾鰭を上げて潜っていくところだった。
僕たちの乗っているホエールウォッチング船は、クジラに囲まれている。
おそらく、7頭か8頭はいるだろう。遠くに見えたブローも含めると、10頭以上いるかもしれない。
南東アラスカの街ジュノーの港を出航してからまだ20分ほどだが、すでに数え切れないほどのクジラたちと出会っていた。
ぼーっとクジラたちを眺めていると、奄美大島にいるような気がしてくる。
ブローが上がり、テールが上がり、海と森とクジラの気配が残る。
それは毎年見ている光景であり、僕にとっては冬の日常と言ってもよかった。
しかしよく見れば、ここが奄美大島ではないことはすぐにわかる。
プランクトンで満たされた南東アラスカの海はクリーミーで、南国の紺碧の海ではない。
島を覆っているのはおそらくトウヒの仲間だろう。これも、アラスカ針葉樹林を象徴する植生の一つだ。
アラスカの旅も終盤に差し掛かっていた。
ジュノーに辿り着くまでに、フェアバンクス、北極圏、デナリと旅をして来た。
北極圏は圧倒的だった。
東京からシアトルで乗り継ぎフェアバンクスに到着すると、現地在住のネイチャーガイド・河内牧栄さん、そして一緒に旅をする仲間と合流した。
陸路でアラスカ北極圏に入るには、フェアバンクスから北極海までの一本道を進む他選択肢はない。
その距離なんと約500マイル。800キロ近い道のりだ。
僕たちは、世界で最もタフなハイウェイとも言われている「ダルトンハイウェイ」を北に向けて走り始めた。
牧栄さんが運転するバンは300キロ近くを一気に走破し、北緯66度33分を超えて北極圏に入った。
雨降るタイガの森でキャンプを張り、翌朝さらに北へ向けて出発した。
それまで茂っていたシラカバは徐々に見られなくなり、トウヒもどんどんと減り、視界が開けてくる。
僕たちは森林限界を越え、ツンドラ地帯に入ろうとしていた。
アラスカ北極圏の旅がようやく始まる。そんな気配が漂っていた。
そのまま100km以上北上を続け、ブルックス山脈を越える。
ノーススロープと呼ばれる、ブルックス山脈北側の緩やかな斜面に入ると、そこはまさに、視界を遮るものない原野だった。
現地ではカリブーという呼称で親しまれているトナカイたちが、はるか遠くで休んでいた。
北緯66度33分以北、つまりブルックス山脈の南側からすでに北極圏ではあるのだけれど、感覚的には、ブルックス山脈の北側こそが本物の「アラスカ北極圏」なのではないか。
なんとなくそんな気がした。
野生動物を探しながら、ツンドラの原野をさらに北へ向かって進んでいく。
すれ違う人間は、北極海に面した油田で働く作業員と、カリブーを狙うハンターだけ。
当然観光バスなんていないし、望遠レンズで野生動物を撮影しようとしている人とすら出会わない。
そこには、ただただツンドラの原野が広がっていた。
シャワーもなければトイレもない、というかキャンプ場でもないから本当に何もないのだけれど、そんな原野にテントを張って夜を迎えた。
けれど、夜は簡単に訪れなかった。
バーベキューを囲んで、ウイスキーを飲んで、皆で旅への思いを語り合う。
そうこうしているうちに、22時を回り、23時も回った。
それでも、ツンドラの原野は明るかった。
太陽は地平線近くまでやって来てはいるが、それは到底夜と呼べるような明るさではなかった。
僕は生まれてから今日までの37年間、太陽は朝登り夕方沈むものだと思っていた。
言葉の上では白夜も極夜も知っていたし、それらに関連するエッセイなんかもいくつか読んだはずだ。
でも僕は、結局のところ、自分の住む世界のこと以外は何も知らなかったのだろう。
僕にとっての初めてのアラスカは、広大な原野でもなければ躍動するカリブーでもなく、日付が変わる頃ようやく沈もうとする太陽だった。
世界が一つではないということを、その時僕は全身で感じた。
それは感動ともちょっと違う、特別な、強烈な体験であり、強烈でありながら、その感覚は僕の中にすっと腰を下ろしたのである。
ジャコウウシ
僕たちはアラスカ北極圏をさらに北へ進んだ。
そのまま行けば、最後は北極海に面した街デッドホースに辿り着く。
そしてデッドホースまでのエリアが、ジャコウウシの生息地だった。
ジャコウウシは、氷河期からの生き残りと言われている。
氷河期といえば、思い浮かぶ動物はマンモスだろう。
他にも色々いたのだろうけれど、まあ、多くの人が想像するのはマンモスに違いない。
つまり、ジャコウウシはマンモスと一緒に暮らしていた動物だ。
だから、というわけでもないだろうが、ジャコウウシはウシというより、マンモスに近いような風貌をしている。
顔はウシというよりバッファローで、体はマンモスで、でもマンモスよりは小さくて……
というのは、もちろんネットや写真集で見たジャコウウシのイメージだった。
僕はそんなジャコウウシを、北極圏にしか生息していないジャコウウシを、どうしても見てみたかった。
ダルトンハイウェイを北上しながら、どこかに彼らが潜んでいないか目を光らせる。
原野の果てに、黒い塊が点のように見える。
ジャコウウシに違いない。
そう思って双眼鏡で確認すると、岩だった。
ということが繰り返された。
岩ならまだ間違っても仕方ないかと思えるが、ヤナギの木さえもジャコウウシに見えた。
そうしてジャコウイワやジャコウイシ、ジャコウヤナギに騙される時間が永遠と続いた。
実際には数時間くらいなのだけれど、それは永遠のように感じられた。
沖縄や奄美で、なかなか現れてくれないザトウクジラを探している時と全く同じ気持ちになった。
結局捜索初日は見つからず、2日目に、遙か遠くにポツンと佇むジャコウウシの雄を見つけた。
もちろん見つけたのは僕ではなく、ガイドの牧栄さんだ。
「ほらあそこ!」と言われても、僕には最初、点すら見えなかった。
ホエールスイムを始めてからの数年、「ブロー」と言われても自分には何も見えなかった頃を思い出した。
双眼鏡越しにようやく僕にも見えたけれど、それは「出会った」という距離ではなかった。
「存在を確認した」とでも言えばしっくりくるだろうか。
ポツンジャコウウシの他にも、遠くに雌と子供の群れなども見つけたが、接近を試みられるような距離ではなかった。
距離の問題だけでなく、常にジャコウウシと僕たちの間には川があった。
もちろん比喩的な意味ではない。数日間続いた大雨で増水した川が、物理的に存在していた。
遠かったけれど、それでもジャコウウシを見ることができて感動した。
というのは建前で、もっと近くで出会いたかった。
それは僕だけでなく、そこにいた全員の本音だろう。
ジャコウウシ捜索3日目。
僕たちはすでに北極圏最後の目的地、デッドホースに到着していた。
つまり、ここからは帰り始めないといけない。
個人的にはジャコウウシと近くで出会えるまでずっとこの辺をウロウロしていたかったけれど、そもそも旅の目的がジャコウウシ探しというわけでもないし、スケジュールも決まっているので、僕たちは帰り始めなければならなかった。
ダルトンハイウェイを南下し始めて、1時間近くが経った頃だったろうか。
左前方、10時の方向に黒い塊が見えた。
それは僕が肉眼で見てもジャコウウシとわかるくらいの距離だった。
車を止めて、詳しい状況を確認する。
オスのジャコウウシは、やはりポツンと、ツンドラに佇んでいた。
そして彼は明らかに、川の向こうではなく、こちら側にいた。
牧栄さんの指示に従って、僕たちもツンドラに下り、少しずつジャコウウシに近づこう……
とした、その時である。
佇んでいたジャコウウシが歩き出した。僕たちのいる方向に。
僕たちは急いでヤナギの影に隠れ、彼が近くを通り過ぎてくれることを祈った。
彼は人間を気にしつつも、それほど脅威だとは感じていないようで、方向を変えずにそのまま近くまでやってきた。
ヤナギの影から望遠レンズだけを覗かせて、連写する。
なんか俺、スターリングラードのスナイパーみたいでカッコいいな、と、中学生みたいなことを思った。
ジャコウウシは、そのまま北へと歩き去っていった。深追いすることはなかった。
緊張から解き放たれ振り返ると、牧栄さんが目に涙を湛えながら微笑んでいた。
ああ、今自分が経験させてもらっていることはそういうことなんだな、と思った。
圧倒的な自然を前についつい忘れてしまいがちだけれど、今見ている自然は、色々なものの積み重ねの上にある。
僕はその時、ジャコウウシと出会ったのではなく、牧栄さんを通してアラスカ北極圏と出会ったのだった。
ひとり
そこから3日ほどかけてダルトンハイウェイを南下し、途中宿に泊ったりキャンプをしたりしながら、僕たちはフェアバンクスに戻った。
フェアバンクスの空港で、牧栄さんと、一緒に旅をした仲間と解散した。
アラスカの旅が終わってしまったような気がした。
実際には、まだ半分も終わっていなかったのだけれど。
フェアバンクスでレンタカーを借りて、デナリ国立公園まで移動した。
ここからは完全に一人旅だ。
デナリと言えば、おそらくアラスカで最も知名度のある野生動物の生息地。
アメリカの国立公園として、きちんと管理された場所だ。
当然、僕みたいに海外から来た観光客が、自由に歩き回ることはできない。
デナリ国立公園の中心部に入るためには、一日に10本以上出ているバスに乗る必要がある。
デナリで何をするか、実はあまり考えていなかったので、ひとまず多くの観光客に混じってバスに乗った。
40人乗りくらいだろうか。車内は満席だった。
見たところ、日本から来ている人はいない。アメリカ国内旅行者が多いようだ。
運転手がジョークを交えながらデナリの案内をする。
とは言っても、僕には何を言っているのかほとんど聞き取れない。
みんなが笑っているからジョークなんだろうと思っただけだし、デナリにいるんだからデナリの話をしているんだろうと思っただけだ。
誰が悪いわけでもないし、というか悪いとすればアメリカにいるのに英語ができない僕が悪いのだけれども、やはり疎外感を感じた。
道中、立派な角を携えた雄のカリブーや、3頭の仔を連れたグリズリーに出会った。
どちらもアラスカで是非とも見てみたかった動物だ。
でも、心の奥底から湧いてくるような感動はなかった。
アラスカの大自然の中で、満席のバスの中から動物を見るという行為に、僕は違和感を感じていた。
身体性を失った状態で生き物たちを見ても、それはどこか、映画を見ているようだった。
自然とのつながりを感じることはできず、サファリパークにいるような気にさえなった。
もちろんデナリが悪いわけでも、バスが悪いわけでもない。
ただ単純に、それは僕自身が一人の観光客にすぎないということだった。
必要な知識と技術を習得した上でデナリに通い、あるいは暮らし、現地でもコミュニケーションが取れるようになれば、その土地と深く関われるだろう。
関わりの深さによって、得られる喜びも変わるはずだ。
結局のところ、それはアラスカだろうが沖縄だろうが、同じことなのかもしれない。
毎日疎外感を感じながらバスに乗るのも辛いので、デナリではその後、できるだけ人のいなさそうなトレイルを選んで、日々歩いていた。
デナリに限らず、アラスカの森に入れば必ずアカリスが出迎えてくれた。彼らは秋になると、餌探しのために活発になるらしい。
カリブーやムース、グリズリーと出会えなくても、リスたちの声を聞きながら森の中を歩いているだけで、僕は幸せだった。
デナリから一度フェアバンクスに戻り、飛行機を乗り継いで南東アラスカのジュノーに向かった。
ホエールウォッチングの初日、僕は残念ながら、デナリで感じたことをまた同じように感じてしまったのである。
ボートには、デナリのバスほどではなかったにせよ、欧米からクルーズ船で来た観光客がたくさん乗っていた。
クジラは出航してすぐに見つかったし、聞き取れないけれど、ガイドさんも色々解説してくれている。
だから、特に何かに不満を覚えたわけではないし、やはり誰も悪くない。
ただ、漂っている空気の中に予定調和を感じていたのは事実だ。
いつもと同じコースを回って、なんとなくクジラをたくさん見て、はいよかったねという感じがした。
クジラを探す過程もないし、1頭、あるいは1群をじっくり観察するということもなかった。
とはいえ、それも仕方ないことなのかもしれない。
クジラがいつもそこにいるのだとしたら、見つからないふりをするわけにもいかないだろう。
というか一般的に、ツアー参加者はクジラを一目見てみたいと思っているのだろうから、わざわざ他のクジラを探しに行くなんてことは誰も望んでいない。
それから、僕が普段観察している奄美・沖縄とアラスカとでは、同じザトウクジラでも、状況が全く違うということもある。
沖縄や奄美では繁殖行動を観察しているので、親子にエスコートがついているなとか、雄と雌のペアかなとか、そんなことを常に考えているし、ひとつの群れをじっくり観察する。
一方アラスカでは、クジラたちは基本的に採餌している。
バブルネットフィーディングなんかの時はまた違うのかもしれないが、僕が見ている限り、それぞれが小魚やらオキアミやらを追って、自然と餌が多い場所に集まってきているような感じだった。
なのでそもそも、群れという概念がちょっと違うのかもしれないし、それぞれのクジラが同じ海域で縦横無尽に動き回っているから、1頭を追うことも難しい。
そんな事情もあるから、僕が感じた違和感は、単純に状況の違いからくるものとも言えるかもしれない。
虹
さらに言えば、ジュノーに辿り着いた時点で、僕は精神的に疲弊していた。
フェアバンクスを離れてから一週間近く、苦手な英語だけで生活してきた。
日本を出たこと自体が十数年ぶりだし、これまでの海外旅行なんてせいぜい3泊4日くらいのものだったから、もちろんこんな経験は初めてだ。
精神的な疲れも、その場の状況をネガティブに捉えてしまった一因に違いない。
ホエールウォッチング初日の夜、一人宿でビールを飲んでいると、早く日本に帰って居酒屋で仲間と飲みながら他愛ない話がしたいな、なんて思いが頭をよぎった。
とはいえ飛行機も宿も予約してあるし、本当に日本に帰るわけにもいかない。
「アラスカでザトウクジラを見たい」という明確な目的があってジュノーに来ていたから、ホエールウォッチングも日本にいるうちに3日間予約していた。
嫌々とまでは言わないまでも、あまり気持ちが乗らない状態で2日目のホエールウォッチングに出かけた。
乗船すると、僕以外のお客さんは全員入れ替わっていた。
出航すると、前日と同じ場所にクジラがたくさんいた。
南東アラスカは、アラスカの中でも特に雨の多い地域だ。
そのため、木々は大きく育ち、その密度も濃い。
艶やかな森にかかるブローは、少なくとも僕がこれまで見てきたブローの中でも、とびきり美しかった。
確かにそれは美しかった。
それなのに、どうして心が昂ってこないのだろう。
クジラを30分ほど観察した後だったろうか。
ガイドがシーライオンを見に行こうと言った。
なぜその時だけばっちり英語が聞き取れたのかというと、前日も同じセリフを聞いていたから。
そう、僕は前日もシーライオンこと、アシカを見ていたのだ。
やつれた僕の心は、「はいはい、昨日と一緒ね」とつぶやいていた。
シーライオン自体は可愛かったし、やはり誰も悪くないのだけれど、浮標に乗っていて、どうにも見せ物っぽかったのである。
シーライオンが見えて来ました!とガイドからアナウンスがあったので、一応腰を浮かして船の前方を見てみた。
すると、どうも昨日とは場所が違うようだ。他にもシーライオン浮標があるのだろうか。
だが、浮標は見えなかった。その代わりに大きな島が見えた。
船首に出て島の方をよく見て、驚いた。
数えきれないほどのシーライオンが、まるで波に打ち上げられたかのように寝そべっているではないか。
「こんなザ・ワイルドライフ的な光景があったのかよ!なんで昨日は行かなかったんだよ!」と、思わず笑ってしまった。
先ほどから出ていた虹が島の近くに見えていた。
虹は少しずつ、シーライオンに近づいていた。
もちろん、虹が自分で歩いていくわけではない。
きっと船長が気を利かせて、船を回してくれたのだろう。
あるいは自然の悪戯だろうか。
気づけば虹は、シーライオンたちの背後から始まっていた。
彼らも虹が珍しいのか、一頭、また一頭と目を覚まし、思い思いに虹を見たり、そのまま寝たりしていた。
自然っていいなと思った。
こんな光景は全く予想していなかった。
ふさぎ込んでいた心が少し開いたような気がした。
僕は何か決定的なミスだけをしないように、丁寧にシャッターを切った。
目の前の自然がただ美しく、夢のようで、余計なスパイスはいらなかった。
自分で言うのもあれだけれど、なかなかいい写真が撮れたんじゃないか、と思う。
写真を見て、何か感じてくれる人もいるかもしれない。
でもきっと、この写真からは、シーライオンたちののんびりとした鳴き声は伝わらないだろう。
虹が現れてから消えるまでの時間の長さも、あるいは短さも感じられないはずだ。
海上を吹き抜ける風や、近くで息づくザトウクジラの気配まで写真に載せることができたなら、それはどんなに素敵なことだろうか。
アラスカの旅は、身体性を持って自然を感じることの意味を教えてくれた。
僕は写真も文章も大好きだ。写真や文章で人の心は動かせると思っているし、実際自分の心が動かされたから今がある。
しかし、写真や文章を通して触れることと実際に感じることの間には大きな差があると、今、強く思う。
僕は星野道夫の作品を通して、アラスカを知った。
でも、2023年のアラスカに、星野道夫の世界はなかった。
少なくとも、僕の旅の中にはなかったと言えよう。
ではそれが悲しいことだったのかというと、全くそうではない。
これまで憧れていたアラスカではなく、自分自身の感覚を伴った新しいアラスカが、今回の旅を通して目の前に立ち現れた。
一歩一歩踏み出す足を包み込む、ツンドラの感触。
夏の終わりに体温を奪い続ける、容赦ない烈風。
いつまでも沈もうとしない、極北の太陽。
それらは、アラスカを訪れる前には想像もしていなかった。
けれど今では、僕の中のアラスカを構成するかけがえのない要素になっている。
8月下旬、ブルックス山脈には初雪がちらついていた。
すでに山々は、真っ白な新雪に包まれているだろう。
そこには点々と、オオカミの足跡がついているかもしれない。
今、そんなことを想像できるということは、どんなに幸せなことだろうか。
僕はもう一つの世界を知ってしまった。
きっと、そこに帰らずにはいられないだろう。
目を瞑って横になれば、今もツンドラの柔らかさを感じられる気がした。




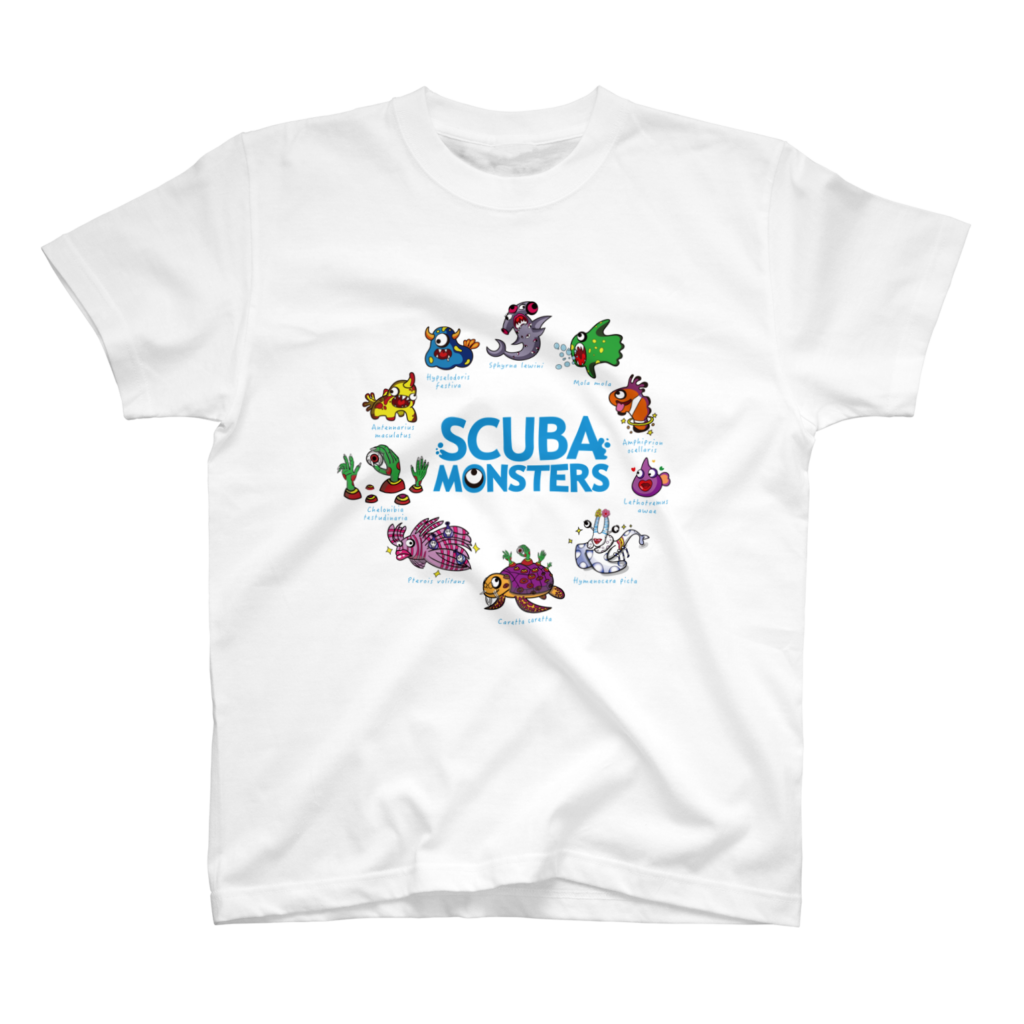


















この記事へのコメントはありません。