ちょっと待って!その浮上速度、本当に安全!?
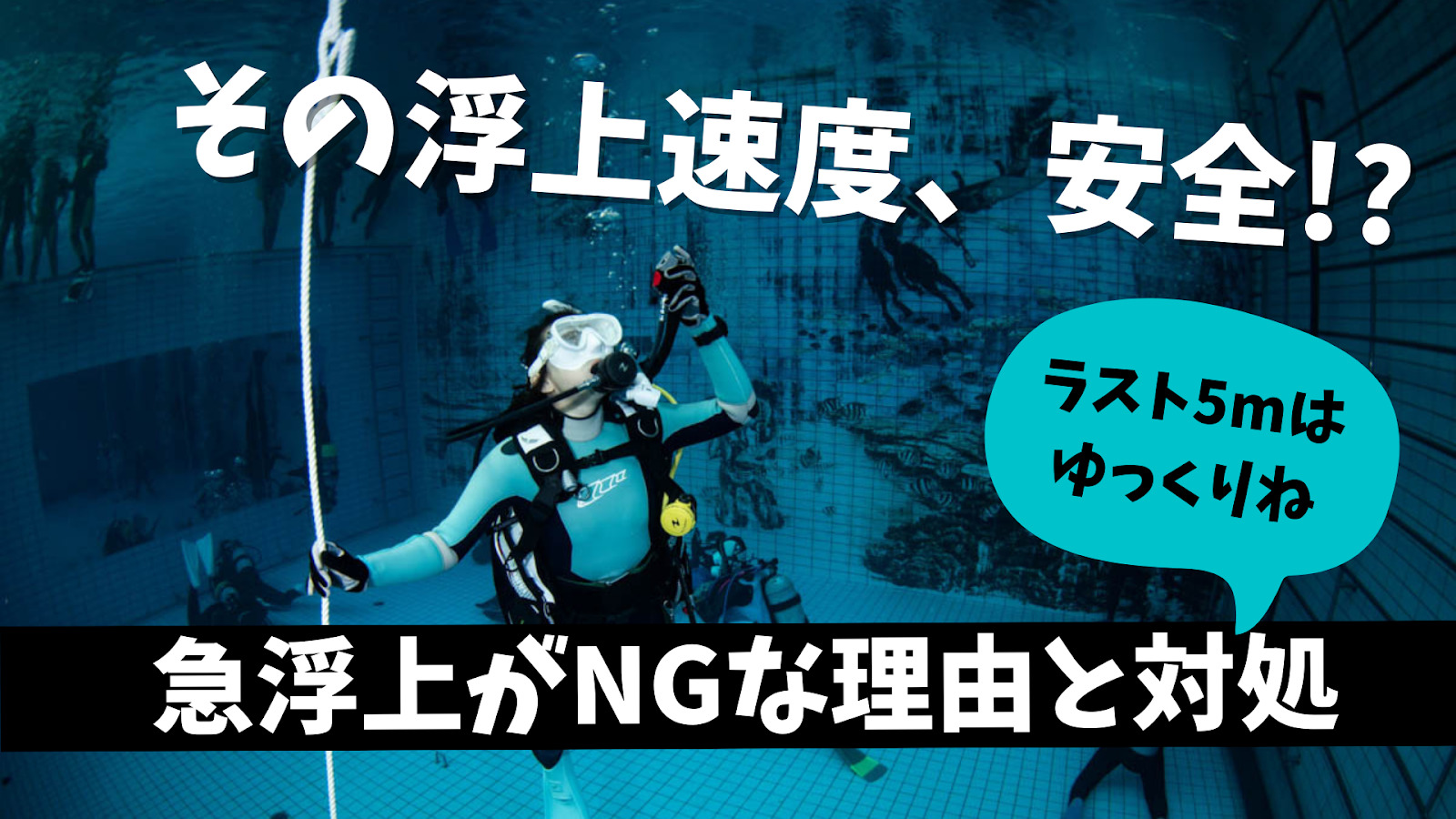
ダイビング終了後に必ず行うことといえば浮上。
一目散に水面に向かって泳ぐような浮上の仕方をしてはいけないということは、ダイバーの方であればご存じの事と思います。
今回は、そんな浮上速度について、詳しく見ていきたいと思います。
急浮上をしてはいけない理由
急浮上をしてしまうと不意に水面の船やダイバーなどにぶつかってしまったり、リバースブロックを起こしてしまったりと、様々な不都合が生じるのですが、最も問題になるのが減圧症との関係性です。
ダイビングを行うと、水圧によって体内に窒素が溶け込みます。
溶け込むこと自体に問題は無いのですが、浮上して水圧が無くなった際に、体内の窒素の一部が溶け込み切れなくなると、体内に気泡が発生し、減圧症を発症してしまうことになります。
浮上後に体内に窒素が溶け込み切れなくなる理由としては、そもそも窒素をため込み過ぎているという場合もありますが、急浮上も原因になりえます。
窒素のため込み過ぎに関してはダイブコンピューターやダイブテーブルを利用して管理するため、気を付けていればため込みすぎを防ぐことは簡単にできます。
通常であれば、溶け込み切れない窒素が出ることの無い様、ゆっくりとだましだまし浮上を行うのですが、急浮上してしまうと、本来は減圧症を発症しないはずの体内窒素量でも減圧症を発症してしまうのです。
イメージとしては、炭酸飲料のキャップを非常にゆっくりと開けると容器内部にあまり泡はできませんが、一気に開けると容器内に多数の泡ができますよね。
あれと一緒です。
安全な浮上速度とは?
具体的には毎分18m以下の速度で浮上することとされています。
最近は減圧症の研究も進み、毎分10m以下が推奨されており、多くのダイブコンピューターではこの速度を超えると警告音が鳴るようになっています。
また、指導団体によっては毎分9m、最大でも毎分18mを超えないように、としています。
そうは言っても、潜っている最中に速度を知るのは難しいですよね。
目安として、自分の吐いた1番小さな泡が浮上する速度を超えないこと、とされることも多いのですが、もう少しだけ具体的に考えてみましょう。
分速を秒速に直してみると、少しだけイメージが湧きやすくなるかもしれません。
毎分18mであれば毎秒30cm、毎分9mであれば毎秒15cmです。
では15cmというとどのくらいかというと、多少の個人差はあるものの、親指と人差し指をL字に広げた時、親指から人差し指までの長さがおおよそ15cmです。
余談ですが、日本(をはじめとしたアジア圏)の長さの単位である「尺」は約30.3cm(明治期の日本の定義)ですが、これは親指と人差し指の距離の2倍の長さが元になっています。
「尺」という文字も、この形から来た象形文字なんですね。(諸説あり)
閑話休題。
1秒間に15cmというと、じれったいぐらいにゆっくりな速度だと思いませんか?
必ずそれぐらいの速度で浮上していると、自信を持って言うことのできない方も多いのではないでしょうか。
ビーチダイビングで斜面にそって浮上していくのならまだしも、ボートダイビングなどで垂直に浮上する際は、なかなか難しい速度なのではないかなと思います。
フィンキックの力で浮上を行おうとすれば、すぐにこの速度を超えてしまいますよね。
浮上の際、フィンキックは行わず、BCの空気量と呼吸を調整することで浮上速度をコントロールするようにしましょう。
これがなかなか難しいスキルではあるので、ロープがあればロープに捕まり、ロープをゆっくりとたぐって浮上するというのも良いですね。

なお、遅ければ遅いほど良いかというと、そういう話でもありません。
当たり前といえば当たり前ですが、窒素の吸排出はバランスの問題です。
どんなに浅い水深でも、長くその水深に留まれば、窒素の排出量よりも吸収量が多くなってしまうため、余りにも遅すぎる浮上速度だと、逆に窒素を溜めこむ結果となってしまいます。
具体的には、毎分3mほどの速度になると、逆に窒素を蓄積させてしまうという研究結果が出ています。
急浮上し始めてしまったら
まずは落ち着きましょう。
というのも、人間は焦ってしまうと呼吸が止まってしまうこともしばしば。
呼吸を止めて浮上することほど、ダイビングにおいて危険な行為はありません。
まずは呼吸を止めない(息を吐く)ことを意識しましょう。
万が一急浮上してしまったとしても、息さえ吐いていれば、減圧症に罹患することこそあれ、死に至る可能性はまず無いと思って良いでしょう。(無茶な深いダイビングを行っていれば別ですが……。)
とはいえ減圧症も防ぎたいので、急浮上を止める努力をします。
息を吐くことは、浮力を減らすという意味でも効果的です。
浮上の原因がウエイトを落としてしまったことであれば、浮力調整では対処できないため、何かに捕まるしかないですね。
原因がBC(ドライスーツ)の排気不足であれば排気を行います。
ここで注意してもらいたいのが、浮き始めると、水底に戻ろうとして本能的に頭から水底に向かって泳ぎ始めてしまう方が多いです。
勇気を出して、多少浮上しても良いので身体を起こし、頭が水面方向に来るようにしましょう。
その姿勢にならないと、いくらパワーインフレーターやドライスーツの排気バルブから排気を行おうとしても、うまく空気を抜くことができません。

急浮上が始まってしまうと、姿勢を制御することが難しい場合もあります。
そんな時は、BCのダンプバルブ(肩や腰についている、紐を引くことで排気できるバルブ)から排気を試みましょう。
そのためには、自身の器材やその日使用するレンタル器材のダンプバルブの位置を予め確認しておくことが重要ですね。
それでもダメならフレアリングです。
フレアリングというのは、身体を大の字に広げ、仰向けになることで水の抵抗を増やし、少しでも浮上速度を遅くする方法です。
最も注意すべき安全停止終了後
ほとんどのダイバーの方は浮上速度に気を遣い、ゆっくりとした浮上を心がけていることと思います。
しかし、特にボートダイビングなど垂直に浮上を行う場面で安全停止が終了すると、浮上速度のことがどこかへ飛んでしまっている方をちらほら見かける様に思っています。
安全停止終了=ダイビング終了
ということで気がゆるむのか、エキジットのラダー争奪戦に負けたくないのか(笑)、最後の5mをスッっと上がってしまっていませんか?
本来は、安全停止の後こそ、より気を遣って浮上しなくてはならないのです。
なぜなら最後の5mの圧力変化が1番大きいため。
具体的に考えてみると以下の通り。
水深15m→水深10m:2.5気圧→2気圧:0.8倍:窒素の体積は1.25倍
水深10m→水深5m:2気圧→1.5気圧:0.75倍:窒素の体積は1.33倍
水深5m→水面:1.5気圧→1気圧:0.67倍:窒素の体積は1.5倍
窒素の吸排出は、移動した垂直方向の距離ではなく、圧力の変化が関わっているため、同じ5mを移動するのでも、浅いところほど影響が大きいのです。
おわりに
減圧症を予防するため、正しい速度で浮上することは非常に重要です。
一方で、意図せず浮き始めてしまった別のダイバーの方を見かけると、一目散に駆け寄って行って、ぐいっと水底方向に抑え込んだり、フィンを引っ張ったり、勝手にBCのダンプバルブから排気をしてあげたりするダイバーの方を見かけることがあります。
浮き始めてしまった方のことを思っての行動というのはよくわかるのですが……。
突然抑え込まれたり、引っ張られたら驚いてしまいますよね。
気づかないうちにBCを排気されてしまうと、今度は必要以上に墜落してしまい耳抜きの問題を発生させてしまう可能性があります。
実際、
浮き始めて焦る:ワンアウト
不意に引っ張られて驚く:ツーアウト
BCを勝手に排気されて墜落、耳抜き失敗:スリーアウト
とパニックを起こしてしまい、あわや大事故という場面を見かけたことがあります。
ガイド付きのダイビングで、ガイドの視界に浮き始めたダイバーが入っているのであれば、ガイドに任せた方がお互いのために良いと言えます。
ガイドから離れてしまっている場合やバディダイビングで、どうしても自分がサポートしなくてはならない状況の場合は、必ず相手の視界に入る位置から、サポートするようにしましょう。
浮上速度を気にするあまり、ダイブコンピューターの警告音が少しなっただけでも大焦りという方も見かけることがあります。
もちろん警告音を鳴らさないに越したことはありませんが、警告音が鳴ったからといって、即座に減圧症になるわけではありません。
ましてや前述の通り、ダイブコンピューターの警告音は指導団体が推奨する毎分18mという速度よりも遅い、毎分10m程度で鳴る場合がほとんど。
必要以上に焦る必要はありません。
まずは落ち着いて、一度浮上を止めましょう。
そして、改めてゆっくりと浮上を再開すると良いですね。
そして、しっかりを安全停止を行ったうえで、安全停止後も気を抜かずにゆっくりと水面まで浮上します。
最後に気を抜いて上がってしまうと、せっかくのこれまでの注意が水の泡になりかねませんよ!
実際、水と泡の問題なのですが。(笑)




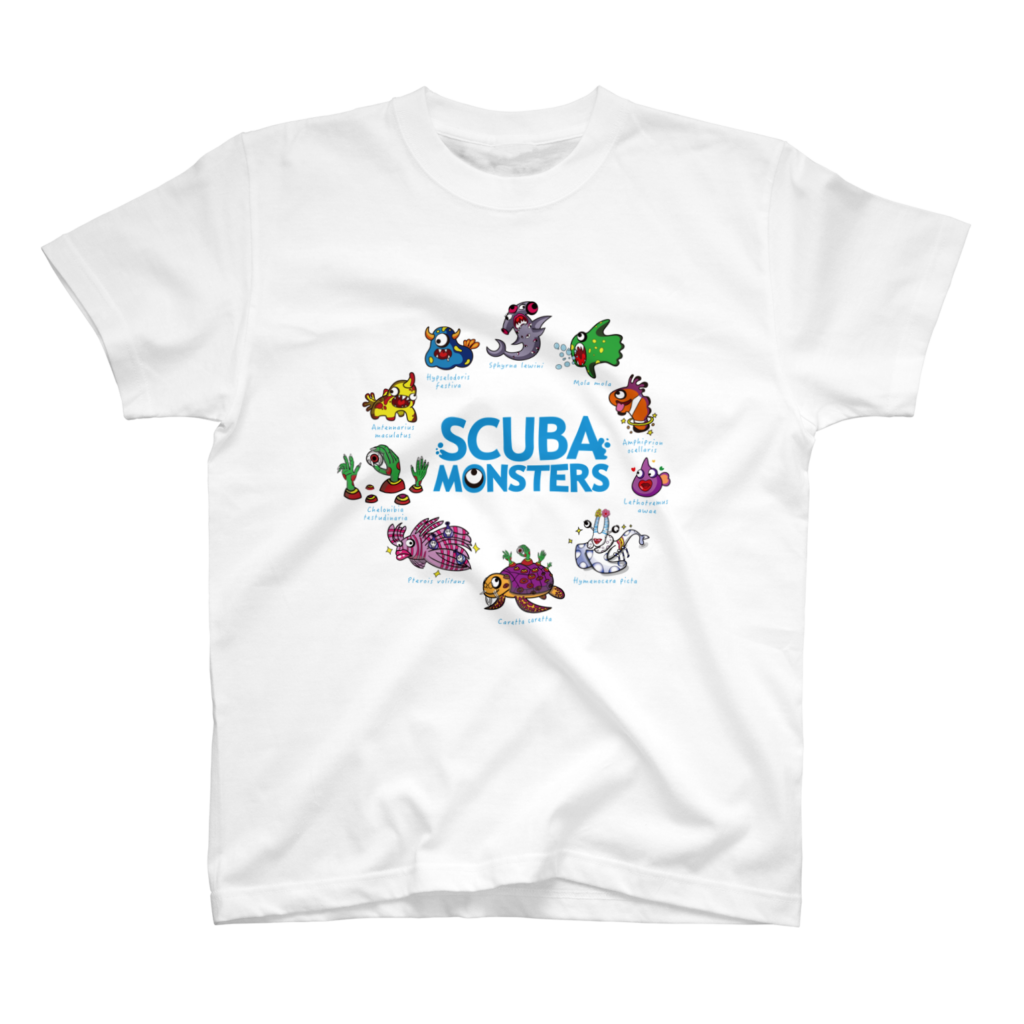

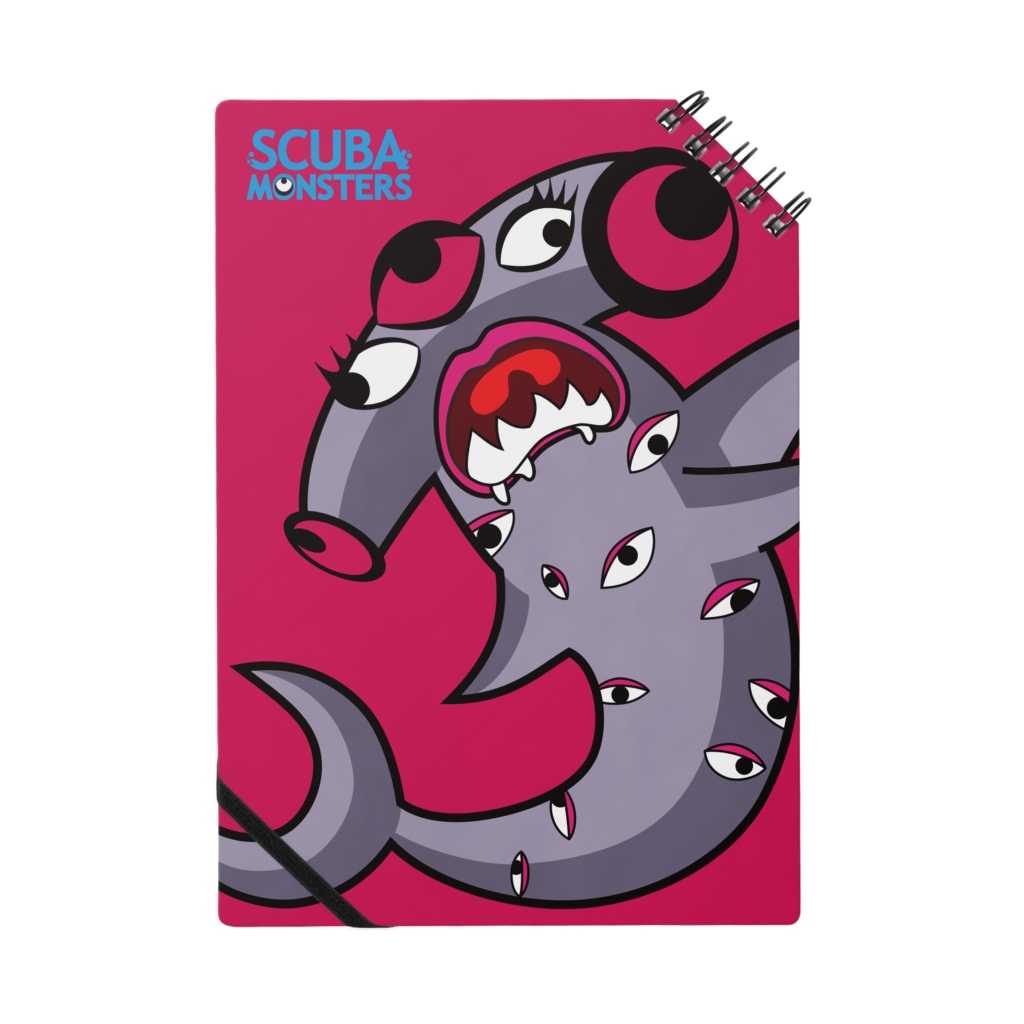


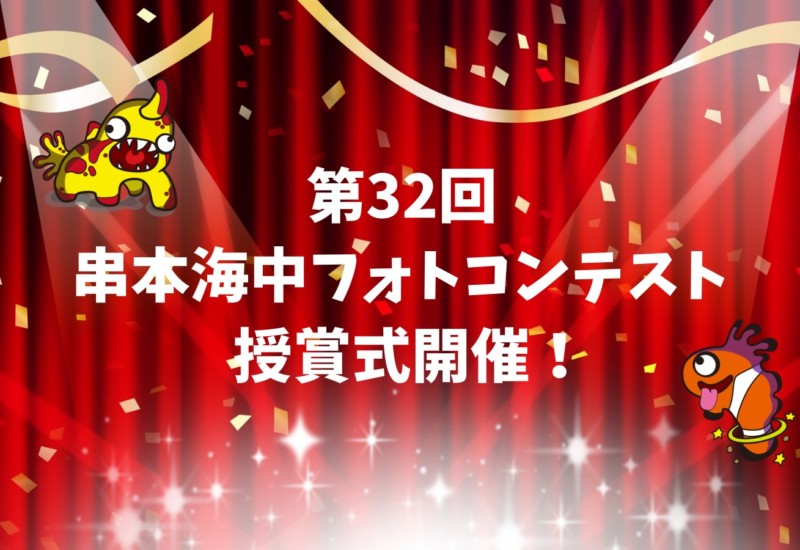







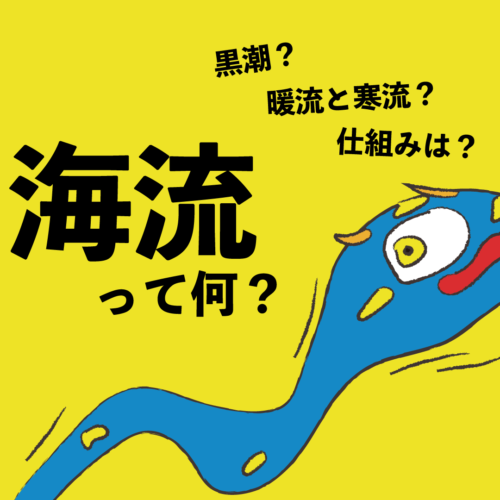

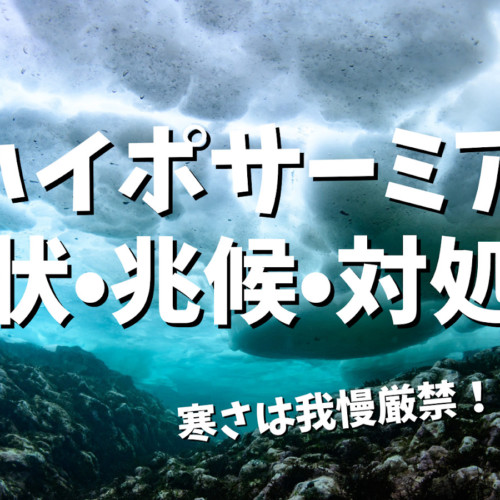



この記事へのコメントはありません。