【考えよう】オシリカジリムシっていう和名はアリなの??
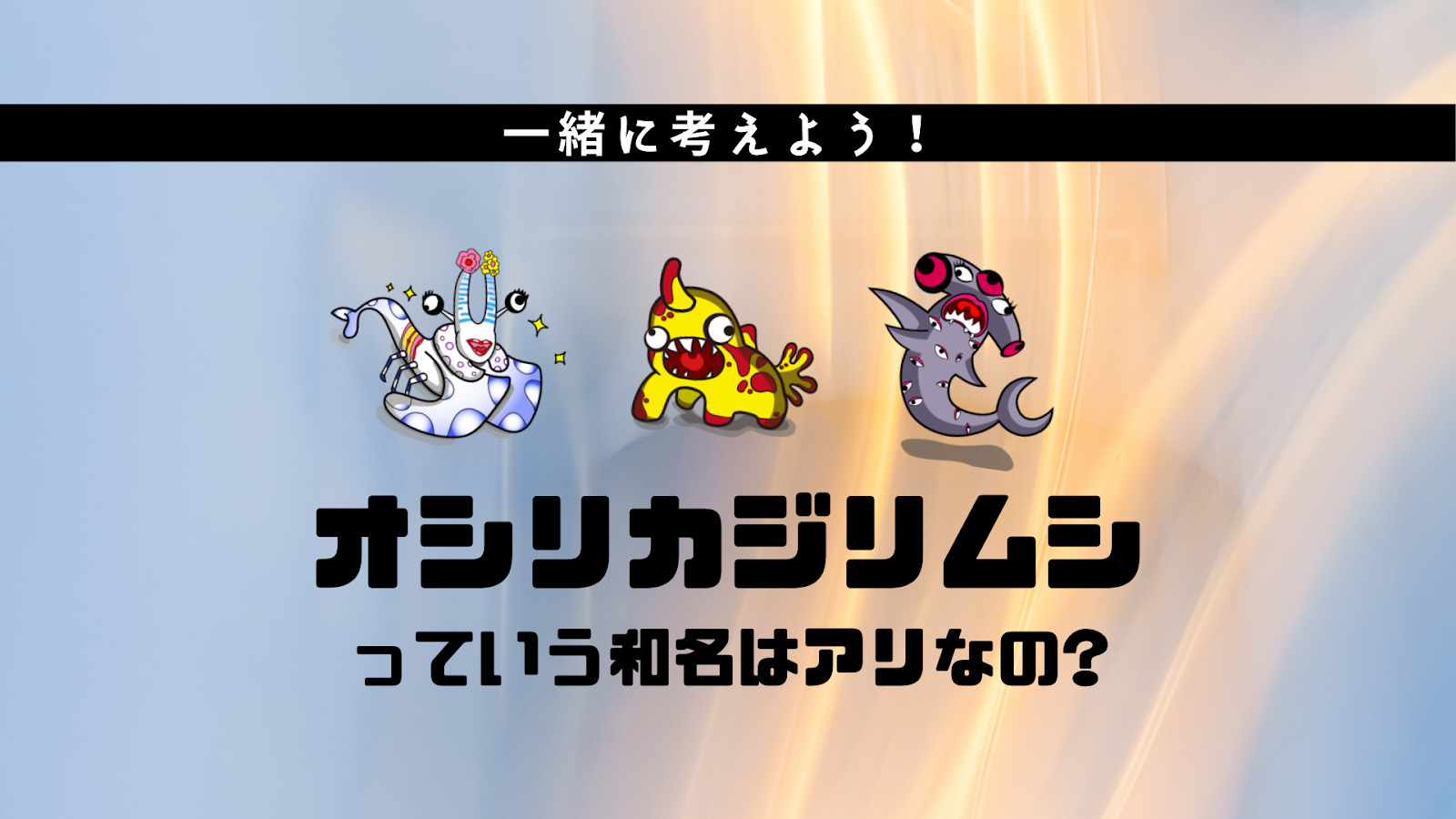
「考えよう」シリーズは、“答えはないけれど語り合いたい”というテーマについて皆さんと深めることを目指す企画です。
受け止め方や考え方は、人それぞれ。
もっと、ダイビングや海のこと、語り合いましょう!
オシリカジリムシのニュース
2022年1月25日、なんともキャッチーなニュースが飛び込んできました。
鹿児島大学は、鹿児島県出水市の干潟で採集したハゼの仲間の尻びれに、体長1ミリ余りの新種の甲殻類が付着しているのを発見し、おしりにかじりつくような様子から「NHKみんなのうた」の人気キャラクターにちなんで、和名を「オシリカジリムシ」と命名しました。
「オシリカジリムシ」と命名 新種の甲殻類 鹿児島の干潟で発見|NHK
新種の甲殻類(カイアシ類)にオシリカジリムシという標準和名が付けられた、というニュース。
各種メディアで大きく取り上げられたので、目に止まったダイバーも多かったのでは??
僕自身、はじめは面白いニュースを見つけたと感じたものの、頭の中ですぐに疑問が追いかけてきました。
果たして、和名としてアリなのか……?
僕は、生物分類学の専門家でなければ、大学などで生物に関する基礎教育を受けてきたわけではありません。
これまでダイビングに関わる中で多くの生物に触れ、生物の名前をたくさん知っているというだけに過ぎません。
ですのでここからのお話は、専門的な見解でもなければ、いずれかを支持する物でもないことをはじめにお断りさせてもらいます。
ちなみに、カイアシ類は、甲殻類(節足動物門、甲殻亜門)のうち、顎脚綱(または六幼生綱)カイアシ亜綱に分類されるものです。
門、綱、科、属といった分類階級の用語に関してはこちらから。
寄生性を持つ種も知られており、寄生生物好きダイバーからはコペポーダという学名(学名については後述)で呼ばれることが多い生き物です。
和名と学名とは
さて、生き物にはそれぞれ和名がついています。
そして、生き物にはもうひとつ、学名というものがついています。
ある生き物を指して、それぞれの国でバラバラな呼び方をしてしまうと都合が悪い。
そんな事情から、世界共通の名前としてつけられているのが学名、当然、アルファベット表記です。(ラテン語)
そして、全ての種に固有の学名がつけられています。
しかし、普段から学名を用いるのは、それはそれで不便です。
国内で使用するには日本語の名前が必要だということで使用されているのが和名です。
もちろん各国でそれぞれ母国語の名前がつけられているわけですが、日本の場合は和名と学名が一対一対応しているという点が特殊です。
当たり前かの様に思われてしまうかもしれませんが、海外では1つの種に対して複数の(母国語での)名前がついていることが珍しくありません。
また、ここからここまで、この魚の仲間は全部XXと呼ぶ、なんて事も珍しくありません。
いかにも日本人の几帳面さが感じられる話ですが、一方で学名と和名を一対一対応させているために、難しい問題も発生します。
それは、後から名前を変えられないこと。
名前を変えるというのは1つの種に複数の名前が生まれることの温床になりかねないからですね。
絶対に変更できないというわけではなく、過去には差別用語を連想させるとして改名が施されたこともありましたが、原則的にはこういったことは起こりません。
ちなみにダイバーに大人気のカエルアンコウは差別用語を連想させるとしてイザリウオから改名された例で、今でもカエルアンコウのことをイザリと呼ぶダイバーもいますね。

話を戻すと、改名できないからこそ和名の名づけは慎重の上にも慎重を期して行われています。
オシリカジリムシという和名への個人的違和感
さて、オシリカジリムシ……。
ここからは、僕が個人的に感じている違和感を挙げていきます。
この先も面白い名前でい続けられる?
まず、50年後、この面白さは伝わるのでしょうか……。
2007年の一大ブームから15年が経過した今、本家おしりかじり虫を思い出すまでに、時間を要したというのが本音です。
ブームの頃であれば、面白い名前として今以上に注目を浴びたでしょう。
また、現在でも多くの人がおしりかじり虫のブームを記憶しているので、注目を集め、面白い名前として機能しています。
これが50年後になったら……。
現役世代の多くは、おしりかじり虫を知らない世代になっているでしょう。
この先も永く、言い得て妙な面白い名前として機能するのであれば、価値ある名前だと思います。
例えばオジサンやミギマキ、ネジリンボウといった魚、もしかすると名付けられた当時は疑問を呈した方もいたのでしょうか。
しかし、これらの名前は今でも、この先も、誰が見ても言い得て妙な名前だと認識できるものだと思います。
50年後、もしくは100年後、本家おしりかじり虫を知らない人々がこの名前を見た時に、上手い名前だなあ、と思ってくれるのか、個人的には疑問が残ります。
とはいえ子ども番組でブームを巻き起こした歌というのは強いもの。
2022年現在、発売から47年が経った『およげ!たいやきくん』は、リアルタイムを知らない僕も知っています。
同様に『おしりかじり虫』も、この先ずっと歌い継がれ、僕の心配は杞憂に終わるのかもしれませんね。
言葉選びは適切?
カイアシ類であれば、●●カイアシとつけるのが筋なのではないかということも頭に浮かびました。
しかし、カイアシは分類として相当に上の区分の亜綱(哺乳類<綱>でいえば、ヒトも牛も獣亜綱です)。
名称の共通性を持たせるのは、種のひとつ上の分類階級である、属レベルが一般的ということを考えると、今回のオシリカジリムシはそれだけで、属の更に上の分類階級である科、それも単一の科を構成するとのことなので、許容範囲ではあるでしょう。
この先オシリカジリムシに近い生き物、例えば縦じまが入っている物が見つかればタテジマオシリカジリムシといった名前になるのでしょうが……。
こちらも、ネジリンボウ属に属するヤシャハゼの例の様に、必ずしも共通性があるわけではないので、気にしすぎかもしれませんね。
一方、ムシという名前も気になります。
ダイオウグソクムシなどの例もあるものの、わざわざムシという言葉を使うべきだったのか。
さらに、オシリカジリに関しても、疑問が残ります。
今回オシリカジリムシは、たった1匹の標本から新種登録されました。
その1匹がたまたまハゼの尾びれに噛みついている状態で発見されたからといって、本当にみんながみんなオシリをカジっているのか。
実はその1匹こそがイレギュラーで、他の個体は頭をかじっている状態で見つかったら……?
一方、このキャッチーなネーミングからは、「少しでも生き物に興味を持ってもらいたい」という意図も感じられます。実際、多くのネットニュースで取り上げられ、普段の生活では知る由もないカイアシ類に注目が集まりました。
カイアシ類は元々、研究があまり進んでいない生き物です。
注目が集まれば研究が進むキッカケになるかもしれません。
少しでも生き物のことを知ってもらうために、注目を集めるような名前を付けようという想いが込められているのでしょう。
良い悪いではなく、楽しみのひとつにしてしまおう
永く通用する名前をつけようという考え方には共感できます。
一方で、少しでも生き物のことを知ってもらうために、注目を集めるような名前をつけようという考え方も理解できます。
世の中の生き物には様々な名前がついており、特にウミウシではインターネットウミウシやキャロットシードミノウミウシなど、果たして”和”名といって良いのかわからないものもあります。
ダイバーにも大人気のマンタが2種に分けられ、一方、しかも、ダイバーがよく目にする方にナンヨウマンタの和名がついた時にも紛糾しました。
ナンヨウマンタの名づけについては、Scuba Monstersで生物解説を寄稿して頂いている播磨先生も疑問を呈しておられました。
僕自身、播磨先生から標準和名についてのお話しを聞く機会がなければ、オシリカジリムシの命名についてアンテナが立つことはなかったかもしれません。
(敏感になりすぎている自覚も少しあります。笑)
でも。
だからこそ。
今回の命名について、興味が湧き、筆を取っていることも確かです。
オシリカジリムシのネーミングが是か非か、僕には分かりません。
法律で正解が決まっているものではないので正しい、間違い、という結論はないと思います。
しかしその中で、様々な考え方に触れ、それぞれの標準和名に多種多様な背景があり、考え出された標準和名であることに想いを馳せて頂ければ、それだけで新たな楽しみが増えることと思います。
例えばホンソメワケベラ、本来はホソソメワケベラとなるはずだったところ、ソとンを取り違えて発表されてしまったことから現在まで定着しています。
今回のオシリカジリムシを含め、新たな標準和名はいずれ定着するのでしょう。
賛否に関わらず、それぞれがどう思うか、議論をしてみるだけでも楽しいのではないでしょうか。
そして、既に定着している標準和名それぞれに、命名者が込めた想いを読み取ることも、また楽しいのではないかと思います。




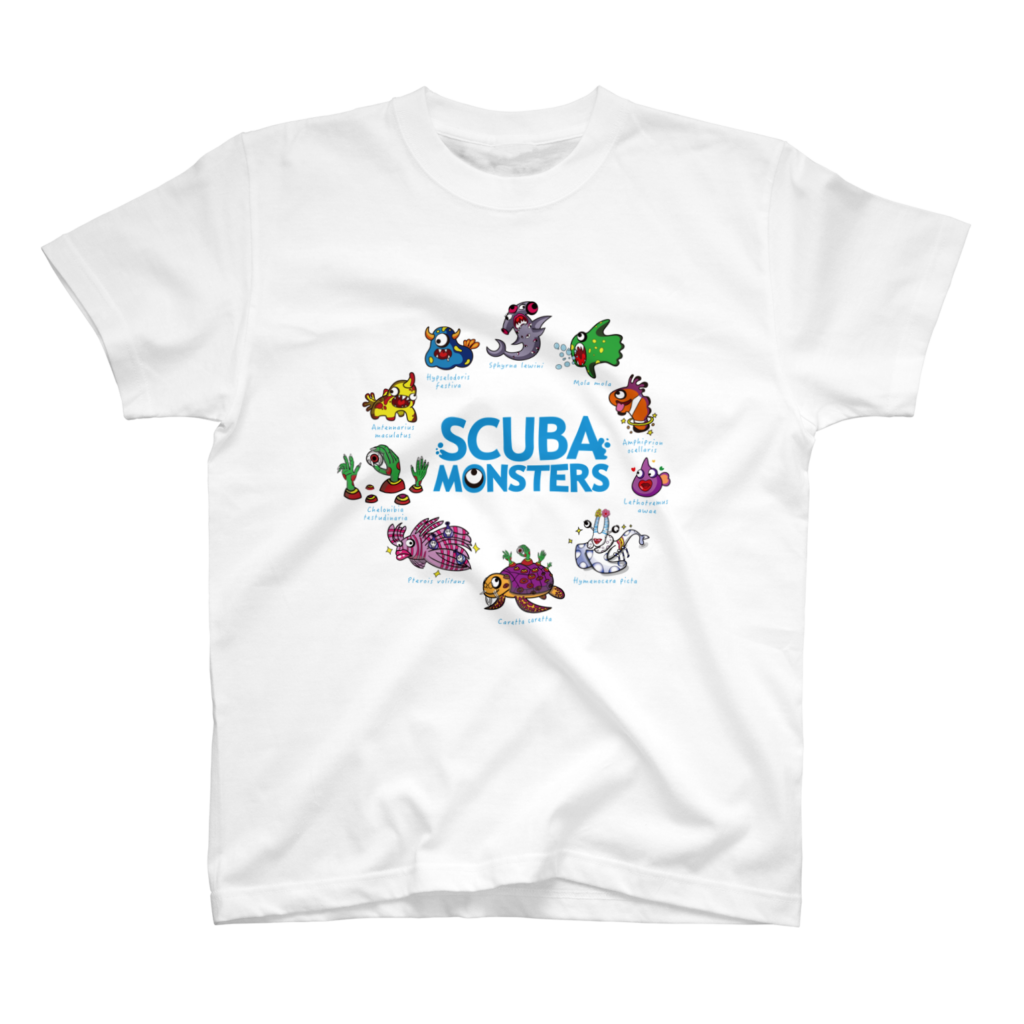

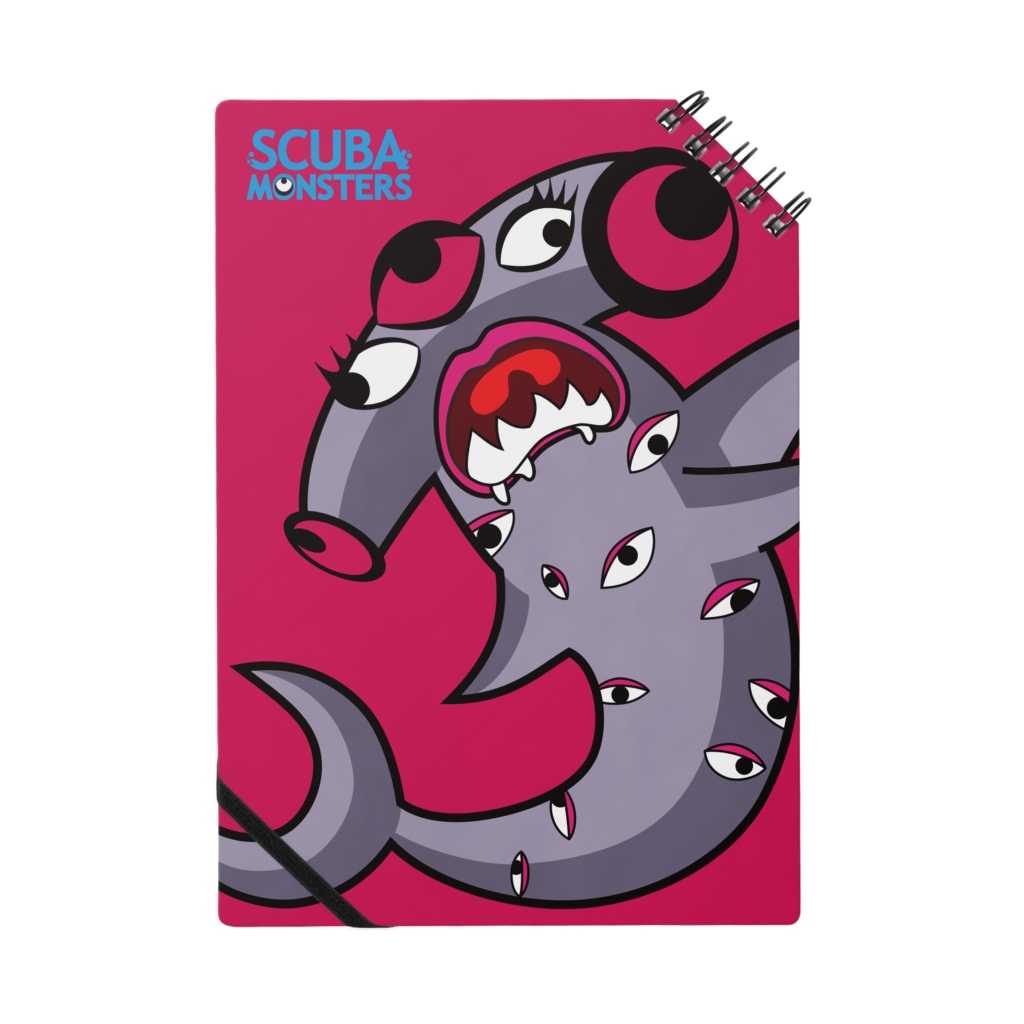


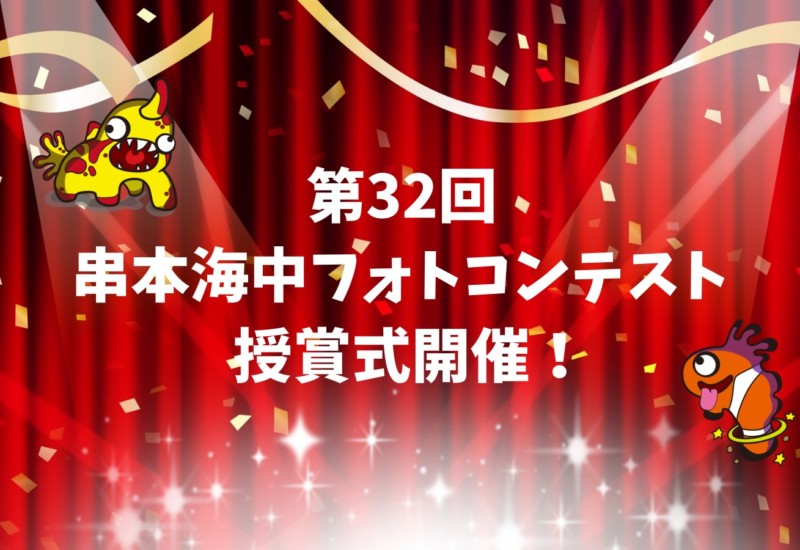













この記事へのコメントはありません。